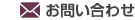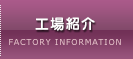菖蒲は魔除けのアイテム
2024年04月30日
こんにちは、マルキヨ製菓広報担当の仲宗根です。昨日今日は雨降りと曇りが交互に来ている沖縄です。ゴールデンウィーク期間中とはいえ、今週は火水木が通常日。今日もみなさん、仕事や勉強を頑張っていることと思います。
今日で4月も終わり、明日から5月。そして、5月5日には「子どもの日」がやってきますね。マルキヨ製菓はその「子どもの日」に向け、期間限定で
「柏もち」をリリースします。今週は「シーミー」用お菓子と、「子どもの日」用お菓子の準備で忙しくしていますよ。
「子どもの日」といえば、「男の子をお祝いする」イメージがあるかと思います。実はこの行事、かつては男の子のための行事というわけではありませんでした。それが、どうして男の子をお祝いするようになったのでしょうか?
バックナンバー
5月5日は五節句の1つ「端午の節句」になります。中国から輸入された五節句ですが、そのうち4つは現在の日本でも行事を執り行います。中国では最も重要視されている9月9日「重陽の節句」だけは、日本に浸透しませんでした。
⇒【端午の節句】
屈原
5月5日「子どもの日」に食べるものといえば、「柏もち」や「ちまき」があります。「柏もち」を食べる理由は次回取り上げるとして、「ちまき」を食べる理由をお話ししましょう。
時は紀元前300年ごろまでさかのぼります。当時の中国は春秋戦国時代。秦・晋・斉・楚・燕・宋・・・といった国々が覇権を争い、後に秦の始皇帝が中国を統一します。
楚(そ)で生まれた屈原(くつげん)男は、非常に優秀な男で、どんどん出世しました。春秋戦国時代に最も力があったのは秦(しん)ですが、楚の中にいる親秦派の連中により、屈原は失脚させられてしまいました。
自分の才能を信じ、その人生を全て国のために費やしていた屈原は大きな絶望を味わいます。そして、自ら川に飛び込み、その命を絶ってしまいました。屈原は国民に愛されていたため、多くの国民が悲しみました。
そこで屈原を慕っていた人々は、彼の命日である5月5日になると、彼が身投げした川へ出向きました。そして米を竹筒に入れて川に投げ込み、それを屈原へのお供え物としたのです。ところがある年、川に屈原の霊が現れ、こう言いました。
「その供物は川に住む龍に食べられている。龍が嫌う楝樹(せんだん)の葉で米を包み、五色の糸で巻きなさい。そうすれば厄除けになり、龍が食べる事はないだろう」
人々は言われた通りにしまし、「葉っぱで米を包み糸で巻く」食べ物を川へ投げ込みました。それが後の「ちまき」です。楚の国民は屈原の命日である5月5日になると、川へ「ちまき」を投げ入れることで屈原を供養し、国の安寧を願うようになりました。
「子どもの日にちまきを食べる」という風習は、このエピソードから生まれたわけです。
「みそぎ」と「魔除け」
5月に入ると暖かい日も増え、日本では田植えなど農作業を始める時期になります。奈良時代の日本では、農作業が始まる時期になると「早乙女(さおとめ)」と呼ばれる若い巫女が、菖蒲(しょうぶ)やよもぎで作られた小屋や神社に出向いて身を清めました。
これは「五月忌み(さつきいみ)」と呼ばれる儀式で、女性は身を清め、田の神様を祀り、豊作を祈願します。
また、5月といえば日本だと梅雨に近い時期で雨がよく降りますが、中国ではその頃、流行病(はやりやまい)が蔓延する事がありました。そのため、屈原の命日である5月5日に合わせ、お祓いや魔除けの行事を行うようになります。
魔除けの効力があるとされる植物「菖蒲(しょうぶ)」の葉を家の門にさし、悪いものが家に入ってこないようにします。沖縄の「シバサシ」という行事と同じですね。菖蒲は酒に入れて飲んだり、風呂に入れ「菖蒲湯」としてつかったりもしますよ。
5月5日は「端午の節句」の他、「菖蒲の節句」と呼ばれる事もありますが、中国のこの風習が由来です。この中国の魔除けの行事が日本にも輸入され、日本でも5月5日に行事を行うようになりました。
日本における「五月忌み」、そして中国から伝わった「菖蒲を用いた邪気払いの風習」。これらが融合して日本における「こどもの日」という行事につながります。
「五月忌み」は女性が行う風習なので、かつての端午の節句は「男の子の行事」というわけではありませんでした。いつ頃から日本における端午の節句は「男の子の行事」として認識されるようになったのでしょうか?
菖蒲・勝負・尚武
日本における「五月忌み」というみそぎの行事、そして中国の邪気払いの風習では「菖蒲」という植物が登場しました。「菖蒲」は「あやめ」という読み方もありますが、「しょうぶ」とも読みます。
「菖蒲(しょうぶ)」は、敵と戦う「勝負(しょうぶ)」や、武道・武勇を重んじる精神を表す言葉「尚武(しょうぶ)」と同じ発音になることが1つ。また、「菖蒲」の葉っぱは鋭く尖っており、武士が持つ刀を連想させることが1つ。
この2点で、「菖蒲」は強い男子をイメージするようになります。
鎌倉時代、武家の間では「鎧(よろい)」や「兜(かぶと)」など身を守る武具を神社に奉納する事で、「家を守り、家系存続を祈願する」風習が生まれました。
武家にとっては子々孫々に至るまで家を守り続ける事が大事であり、そのためにも跡継ぎとなる男子が、しっかりと成長していく事を強く願いました。
「男子の成長を願う」、そして「武具を奉納する」という風習。これが現代の「こどもの日」につながります。子どもの日に鎧兜を飾ったりするのは、ここから来ているわけです。
「端午の節句では、男の子がたくましく成長する事を願う」ようになり、江戸時代まで進むと、徳川幕府が「端午の節句」を公的行事として制定しました。さらに時代が進むと、この行事は一般庶民にも広がっていくのです。
外を歩くと、至る所で鯉のぼりを見かけます。子どもの日を含む金曜日からの連休は晴れるといいですね。マルキヨ製菓は沖縄の皆さんに、連休中も美味しいお菓子を食べてもらえるよう頑張りたいと思います。
今回はこの辺で。
平日は毎日更新。Facebookもよろしくお願いします。
ブログランキング参加中です。よかったらポチッとお願いします。
↓
商品取り扱い店舗
- ・タウンプラザかねひで
- ・イオン琉球㈱
- ・リウボウストアー
- ・㈱丸大
- ・㈱サンエー
- ・ユニオン
- ・コープおきなわ
- ・JAおきなわAコープ
- ・野原食堂(宮古島)
- (順位不同)
※工場でもご購入可能です。毎日製造する商品は異なりますので、事前にお問合わせください。