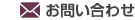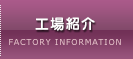上巳の節句
2024年02月20日
こんにちは、マルキヨ製菓広報担当の仲宗根です。朝は気持ちよく晴れていましたが、午後になると曇り空が広がっています。最高気温は26度で、時折見せる晴れ間はなかなかの暑さです。
気がつけば2月も残り10日をきっていました。マルキヨ製菓は次の日曜日にやってくる【ジュウルクニチー】という行事に向け、かなり忙しくしております。
実はこの【ジュウルクニチー】が終わった次の日曜日には「ひな祭り」がやってきます。マルキヨ製菓は毎年この行事に向けてもお菓子を作っているため、さらに忙しい日が続くことになります。
今日はその「ひな祭り」についてのお話となります。
上巳の節句
ひな祭りは「桃の節句」、子どもの日は「端午の節句」と呼ばれますが、この「節句」とは「季節の節目」を意味する言葉で、中国から来ています。
1年を通して、合間合間の区切りを表す言葉に「節句」と「節分」があります。「節分」は以前紹介しましたが、年に4回あります。一方、「節句」は5つあります。
1月7日:人日 (じんじつ)の節句
3月3日:上巳(じょうし)の節句 ※上巳(じょうみ)とも読む
5月5日:端午 (たんご)の節句
7月7日:七夕(しちせき)の節句
9月9日:重陽(ちょうよう)の節句
中国では奇数が重なる日は縁起が良いとされ、五節句が定められています。1月1日の元日だけは年頭という事もあり特別な日。なので1月の節句だけは1月7日にずれ、「人日の節句」として定められています。
例えば「重陽の節句」は日本人はピンと来ないかもしれませんが、中国の方では重要な日とされていますよ。日本人に馴染みがあるのは5月5日の「端午の節句」あたりでしょう。
3月3日は「上巳の節句」と呼ばれています。ただ、中国で「桃には魔除けの効果がある」と信じられているため、そこから「桃の節句」という呼び方もあります。日本における「ひな祭り」は厄除けの行事という事もあり、「桃の節句」の呼び方はマッチしています。
現代の「ひな祭り」は女の子をお祝いする行事ですが、元々は魔除けの行事。そして、魔除けの中心を担っているのは「雛(ひな)人形」です。次はこの「雛人形」に焦点をあて、話を進めましょう。
人形(ひとがた)
今から1700年以上前の3世紀ごろ、中国では「3月上巳(じょうし)の日」に川へ入って「みそぎ」をするという風習がありました。「みそぎ」とは、体についている悪いものをそぎ落とす行為の事です。
中国では陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)に基づき、暦には干支が割り当てられています(「寅の日」「巳の日」など)。「3月の上巳の日」とは「3月上旬の巳の日」という意味です。これが「上巳の節句」の名の由来となります。
「3月上旬の巳の日」は3月3日に限るわけではありませんが、後に「上巳の節句」を3月3日で固定するようになりました。ちなみに2024年「3月上旬の巳の日」は3月6日水曜日になります。
特にこの日は「己巳の日(つちのとみのひ)」と呼ばれ、60日に一度やってくると言われる吉日とされていますよ。
日本では奈良時代ごろ、中国のみそぎの習慣が伝わってきました。そしてまず、貴族の間で広まっていきます。3月上旬はまだまだ寒い時期という事もあり、根性のない日本貴族は寒い日に川へ入る事はありませんでした。
「身代わりを川に入れよう」という発想になるのが当時の貴族。木や藁を人の形にしたものを川へ投げ入れ、それを「自分の身代わり」とみなす事で「みそぎを行った」事にしたのです。身代わりを立てみそぎを行う事に、意味があるのか個人的には疑問です。
その身代わりの事をを「人形(ひとがた)」と言い、これが「雛人形」の原型と言われています。平安時代になると、高い役職とされる陰陽師が紙で「人形」を作ります。
今から1000年以上前に書かれた源氏物語の中に「自分の身代わりをたて、みそぎをさせ厄払いとする」という記述があり、主人公・光源氏も人形を流しています。その時代、少なくとも高い位の人達にとって「みそぎの行事」は、よく知られていたようです。
ちなみに令和の現代でも、鳥取や奈良など一部の地域では人形を川に流し、それを持って身を清めるという行事が残っています。これは「流し雛」や「雛流し」と呼ばれる行事です。
1000年以上も続く「流し雛」が、「ひな祭り」の起源の1つと言われていますが、当時は「みそぎの行事」であって、「女の子の行事」というわけではありません。
雛(ひいな)と天児(あまがつ)
みそぎとして使われた「人形(ひとがた)」は、雛人形の原型の1つですが、他にも「雛人形」に繋がるものが2つあります。
1つは平安時代の貴族の娘達の間で流行った「ままごと」で使われた、紙で作られた人形。この人形を「雛(ひいな)」と呼び、それを使ったままごとを「雛(ひいな)遊び」と呼びました。「雛祭り」の「雛」、「お雛様」の「雛」はこの呼称から来ています。
そしてもう1つ。平安時代には、赤ちゃんの枕元に布製の人形を置く習慣がありました。赤ちゃんに憑こうとする悪い物をこの人形が吸いよせ、赤ちゃんを守るというのがその役目です。
この布製人形を「天児(あまがつ)」(または「這子(ほうこ)」)と呼び、これもまた源氏物語の中に登場します。この習慣は江戸時代以降も続き、その頃には天児を男子、這子を女子に見立てて、雛壇に対(つい)で飾ります。
そして女の子が嫁入りする際は、これを持参する。そんな風習が、江戸時代には確立していたのです。「人形(ひとがた)」「雛(ひいな)」「天児(あまがつ)」、これらが融合し、現代の「雛人形」につながる事になります。
中国から伝わった「3月上巳の日に川へ入って、みそぎをする」という風習が、一般庶民の間で「女の子の行事」として広まるのは、江戸時代以降です。その話はまた、来週へ続く事としましょう。
マルキヨ製菓はこの行事に向け「桜もち」と
「ひしもち」の2つを期間限定商品としてリリースします。【ジュウルクニチー】との兼ね合いもあり忙しいですが、旧暦の行事も新暦の行事もしっかり対応していきたいと思います。
そんなマルキヨ製菓の行事用お菓子を是非とも、よろしくお願いします!
今回はこの辺で。
平日は毎日更新。Facebookもよろしくお願いします。
ブログランキング参加中です。よかったらポチッとお願いします。
↓
商品取り扱い店舗
- ・タウンプラザかねひで
- ・イオン琉球㈱
- ・リウボウストアー
- ・㈱丸大
- ・㈱サンエー
- ・ユニオン
- ・コープおきなわ
- ・JAおきなわAコープ
- ・野原食堂(宮古島)
- (順位不同)
※工場でもご購入可能です。毎日製造する商品は異なりますので、事前にお問合わせください。