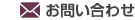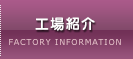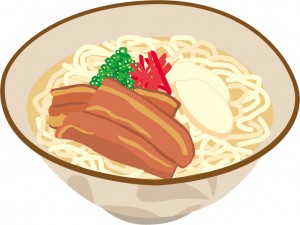沖縄そばの日
2022年10月18日
こんにちは、マルキヨ製菓広報担当の仲宗根です。今日は珍しく、朝起きたときに肌寒さを感じました。それもそのはず、今日の最高気温は24度で最低気温は21度だからです。つい3日前までは日中30度あったはずなのに、急に気温が落ちました。
久しぶりに今日は一日、クーラーを使用しない日になりそうです。ただ、明日からまた少しずつ気温が上がるようなので、三寒四温といった感じですね。
昨日10月17日は「沖縄そばの日」という事で、県内の多くのメディアで取り上げられていましたね。私も「沖縄そばの日」がある事は知っていたし、「そば粉を使わない沖縄そばが、そばとして認められた」事をきっかけに制定された日というのは知っています。
ただ、こまかい所までは分からないので、この機会に色々調べてみましたよ。みなさんは「沖縄そばの日」についてどこまでご存じですか? みなさんの好きな「沖縄そば」は何ですか? お気に入りの店はありますか?
今回は、そんな「沖縄そば」に関するお話です。
「支那そば」から「琉球そば」へ
琉球における麺料理の起源は琉球王朝時代にまでさかのぼり、中国からの使者・冊封使をもてなすための料理として出されたと言われています。
現代の沖縄そばは小麦粉100%の麺で作られていますが、小麦使用の麺料理が一般的に普及するのは明治時代以降。すなわち、すでに琉球王朝がなくなった後になります。
なので冊封使への接待料理として出されたのは、今で言う沖縄そばとは違うものだった事が推察できます。沖縄そばの直接のルーツは、日本人が連れてきた中国の料理人が、那覇市辻(つじ)の遊郭の近くで開いた「支那そば屋」だと言われています。それが明治時代の後期。
志那そば屋をきっかけにそば屋が増えていき、大正時代に入ると一般庶民の間でも気軽に食べられるようになっていきました。やがて、支那そばは沖縄独自の進化を遂げていく事になります。
ねぎや沖縄のかまぼこ、豚肉が具材として使われ、紅ショウガもトッピングとして麺と一緒に食べられるようになります。当初は濃かったスープも現在のように薄い色になっていきました。
そして、コーレーグス(島唐辛子の泡盛漬け)をそばにかけるというスタイルも確立していきます。コーレーグースはかけ過ぎると味がきつくなりますが、ちょうどいい感じでかけると、より美味しくなるんですよね。
沖縄独自に発展していった志那そばは、「琉球そば」と呼ばれるようになります。
戦争後に発展
先の沖縄戦により、県内のそば屋は姿を消していく事になります。ご存じの通り、戦後は米軍占領下におかれた沖縄。やがて小麦粉が流通するようになると、県内各地でそば屋が復活していきます。
特に戦争で夫を亡くした女性達が収入を得るために新しいそば屋を立ち上げていきます。沖縄そばは手軽に食べられますし、お店としても客の回転率がいいため、店の数が増えていきます。まさに需要と供給が合致して、そば屋が発展していったわけです。
「支那そば」から「琉球そば」、そして「沖縄そば」と呼ばれるようになったのは戦後になってからです。
そば屋が増えると、それぞれの店で趣向を凝らしたオリジナルのそばが現れます。宮古の「宮古そば」、八重山の「八重山そば」など、他にも「○○そば」という呼称はたくさんありますよね。
「沖縄そば」は「沖縄を代表するソウルフード」として、さらに発展していく事になります。しかし、ここで沖縄そば界にとっては最大の壁が立ちふさがります。
1972年に沖縄が本土復帰をして4年後の1976年(昭和51年)、公正取引委員会が「蕎麦粉を30パーセント以上混合していない沖縄そばを『そば』と表示することはできない」と、沖縄生麺協同組合へ通達してきたのです。
戦後、沖縄のソウルフードとして発展し、「沖縄そば」の呼称も定着してきたのに、それらを「そば」とみなさないというわけなのです。これらの名称は「沖縄風中華麺」に変更しなければならないのです。
地道な努力の末に
皆さんは今まで食べ慣れてきた「沖縄そば」が、突然「沖縄風中華麺」と名前が変わったらどう思いますか? 愛着のある「沖縄そば」を捨てきれない人も多いでしょう。
「沖縄そばは沖縄の食文化だ」として、「沖縄そば」の名称存続を訴えたのが沖縄生麺協同組合理事長(当時)土肥健一を中心としたメンバー。沖縄総合事務局内にある公正取引室に何度も訪れますが、あちらは首を縦に振りません。
すると彼は東京本庁へ出向き、「沖縄そば」の呼称使用のために話し合いを続けます。雨の日も風の日も雪の日も本庁へ通い、1977年、ついに「沖縄そば」の名称を使用する許可が下りました。
ところが、これで終わりではないのです。「沖縄そば」の名称は、沖縄県内のみの使用に限るという条件が付いていたのです。そうなると、沖縄県外では「沖縄そば」を「沖縄そば」として食べられない事になります。
これではいけないと、さらなる交渉を継続。公正取引委員会や全国めん類公正取引協議会まで巻き込む大きな交渉の結果、1978年10月17日、公正取引委員会から「本場沖縄そば」の商標登録が正式に承認されました。ちなみに「本場沖縄そば」は
①沖縄県内で製造されたもの
②手打ち式(風)のもの
③原料小麦粉[タンパク質11%以上、灰分0.42%以下のもの]
④加水量[小麦粉重量に対し34%~36%以下]
⑤かんすい[ボーメ2度~4度]
⑥食塩[ボーメ5度~10度]
⑦熟成時間[30分以内]
⑧めん線[麺の厚さ1.5~1.7mm]切刃番手[薄刃の10番~12番]
⑨手もみ[裁断されためん線は、ゆでる前に必ず手もみ(工程)を行う]
⑩ゆで水のpH8~9
⑪ゆで時間[約2分以内で十分可食状態であること]
⑫仕上げ[油処理してあること]
という12の定義があり、1つでも欠けるとその表示は認められないとされています。
沖縄そばの日
沖縄生麺協同組合は「沖縄そば」の名称使用を認められた10月17日を「沖縄そばの日」として制定。それが1997年の事なので、実は「沖縄そばの日」は制定から25年しか経っていません。もっと昔からあると思っていた人も多いのではないでしょうか?
現在、我々が「沖縄そば」を「沖縄そば」として食べられるのは、多くの先人による努力のたまものなのです。沖縄そばを食べるときはありがたくいただきましょう。
皆さんは、どの沖縄そばが好きとかありますか? 沖縄そばはどこも美味しいのですが、個人的には首里寒川町にある「和和」という店の「和和そば」が一番好きですね。
沖縄そばはどこも似たようなものだろと思っていましたが、こちらの「和和そば」は初めて食べた時に衝撃を受けるぐらい美味しかったです。月に1度以上は、ここで沖縄そばを食べていますよ。
皆さんも是非、快適な「沖縄そば」ライフを送って下さいね。
今回はこの辺で。
平日は毎日更新。Facebookもよろしくお願いします。
ブログランキング参加中です。よかったらポチッとお願いします。
↓
商品取り扱い店舗
- ・タウンプラザかねひで
- ・イオン琉球㈱
- ・リウボウストアー
- ・㈱丸大
- ・㈱サンエー
- ・ユニオン
- ・コープおきなわ
- ・JAおきなわAコープ
- ・野原食堂(宮古島)
- (順位不同)
※工場でもご購入可能です。毎日製造する商品は異なりますので、事前にお問合わせください。